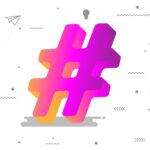「御局(おつぼね)」という言葉は、職場や時代劇で耳にすることがあります。「職場の御局様」などと言うとき、どんな意味で使われているのか気になったことはありませんか?この記事では、「御局(おつぼね)」の本来の意味、歴史的な由来、そして現代での使われ方をわかりやすく紹介します。
1. 「御局(おつぼね)」とは
「御局(おつぼね)」とは、もともと宮中や大名家などで高貴な女性に仕えた女官の地位や、その人の居所(つぼね)を指す言葉です。
しかし現代では転じて、職場などで長年勤務し、発言力や影響力を持つ年長の女性を指す俗称として使われるようになりました。
(読み方)
- 御局(おつぼね)
- 別表記:「御局様(おつぼねさま)」
2. 「御局」の語源
「局(つぼね)」という言葉は、もともと平安時代の宮中で女房たちの居室を指した言葉です。
高貴な身分の女性に仕える女官が住む場所を「〜の局(つぼね)」と呼んでいたことから、その部屋に仕える人をも「局」と呼ぶようになりました。
「御」をつけた「御局(おつぼね)」は、敬意を込めて女官を呼ぶ呼称として使われていました。
たとえば『源氏物語』などにも「〇〇の御局」という形で登場します。
3. 歴史的な「御局」
平安時代から江戸時代にかけて、「御局」は天皇や将軍家に仕える女性たちの中でも、特に身分の高い女官を意味しました。
将軍の正室(御台所)や奥向きの管理を行う役職として重要な地位にあり、政治的・実務的な力を持つ女性も多かったといわれます。
たとえば、徳川家の奥向きを取り仕切った春日局(かすがのつぼね)は、最も有名な「御局」のひとりです。
「春日局」は三代将軍・徳川家光の乳母として絶大な権力を持ち、後世に「御局様」の象徴とされました。
4. 現代での「御局(おつぼね)」の意味
現代では、「御局(おつぼね)」という言葉は主に会社・職場などで長年勤めるベテラン女性社員を指します。
ただし、やや皮肉や冗談めいたニュアンスを込めて使われることが多いです。
(現代的な意味)
- 職場の古参女性社員
- 発言力が強く、周囲に影響力を持つ人
- 時には「怖い先輩」「支配的な人物」という印象を持たれることもある
(例文)
- 新入社員はまず御局様に気に入られることが大切だ。
- 部署の御局がいないと会議が進まない。
- 御局的な立場の彼女は、上司よりも影響力がある。
このように、現代では「御局」は“職場の中心的存在”という意味と、“少し近寄りがたい”という意味が混ざり合って使われています。
5. 「御局」のイメージの変化
かつては「御局」という言葉には高貴で品位のある女性という印象がありました。
しかし現代では、年齢や経験を重ね、影響力を持つベテラン女性という意味に変化しています。
そのため、使う場面によっては相手に失礼と取られることもあります。
公的な場面では避け、冗談や軽い話題の中で使うのが一般的です。
6. 類語・関連語との違い
| 言葉 | 意味 | 違い・使い方 |
|---|---|---|
| 女官(にょかん) | 宮中に仕える女性 | 歴史的・正式な職名 |
| 奥女中(おくじょちゅう) | 大名家や将軍家に仕える女性 | 実務を担う中間層の女中 |
| ベテラン社員 | 長年勤めて経験豊富な人 | 現代的・中立的な言い方 |
| 職場の古株 | 長年いる社員 | 男女を問わず使えるが、ややくだけた表現 |
7. 英語での「御局」表現
英語には「御局」に完全に対応する単語はありませんが、文脈によって次のように訳されます。
| 英語表現 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| senior female employee | 年上の女性社員 | The senior female employee is respected by everyone.(その御局的存在の女性は皆から尊敬されている。) |
| office matriarch | 職場の“女家長”的存在 | She’s the office matriarch.(彼女は職場の御局様だ。) |
| veteran worker | ベテラン従業員 | She’s a veteran worker who knows everything.(彼女は何でも知っている御局的な人だ。) |
8. まとめ
「御局(おつぼね)」とは、もともと宮中や大名家に仕える身分の高い女官を指す言葉でした。
現代ではその意味が変化し、職場で長年勤める影響力のあるベテラン女性を指す表現として定着しています。
ただし、少し皮肉を含むこともあるため、使う際は相手や状況に注意する必要があります。
本来の「御局」は知識・礼儀・品格を備えた女性を意味していたことを忘れずに、正しく理解して使いましょう。