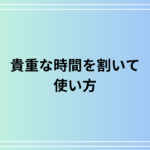「得る(える/うる)」は、知識や経験、利益、権利などを自分のものとすることを意味する日本語の動詞です。日常会話からビジネス文書、文学作品まで幅広く使われ、読み方や使い方に注意が必要です。本記事では、「得る」の意味や使い分け、類義語、例文、文法上のポイントまで詳しく解説します。
1. 得るの基本的な意味
1-1. 定義
得るとは、何かを手に入れる、取得するという意味を持ちます。物理的な物品だけでなく、抽象的な概念や感情も対象に含まれます。
1-2. 読み方
「得る」は文脈によって「える」と「うる」の二通りの読み方があります。 - 「える」:日常的で一般的な読み方。例「知識を得る」 - 「うる」:文語的または硬い文章で用いられる読み方。例「起こり得る」
1-3. 用法の広がり
会話、ビジネス文書、法律文、論文など多様な文脈で使用され、ニュアンスや重みが文脈によって変わります。
2. 得るの使い方
2-1. 知識や情報を得る
学習や調査を通じて知識や情報を取得する場合に使います。 例:「最新の技術情報を得る」
2-2. 経験や技能を得る
時間をかけて身につけるスキルや経験に対して使われます。 例:「海外勤務で貴重な経験を得る」
2-3. 利益や報酬を得る
金銭や利益を手にする場合に用います。 例:「投資で大きな利益を得る」
2-4. 評価や信頼を得る
他者からの評価や信用を築く場合に使われます。 例:「顧客からの信頼を得る」
2-5. 機会や権利を得る
何かを行う権利や機会を手に入れる場合にも用いられます。 例:「コンテストに参加する権利を得る」
3. 得るの文法的特徴
3-1. 活用
得るは下一段活用の動詞で、「得ます」「得て」「得れば」「得よう」などに変化します。
3-2. 「うる」との使い分け
「うる」は可能性を表す助動詞的用法で用いられます。 例:「予測し得る結果」「理解し得る範囲」
3-3. 否定形
「得ない」は「~することができない」「~の可能性がない」という意味を持ちます。 例:「納得し得ない説明」
4. 得るの類義語と違い
4-1. 獲得する
努力や競争によって手に入れるニュアンスが強い。例:「資格を獲得する」
4-2. 取得する
正式な手続きを経て手に入れる場合に多い。例:「免許を取得する」
4-3. 入手する
物品や情報を手に入れることを表し、やや口語的。例:「資料を入手する」
4-4. 受ける
相手からの働きかけによって得る意味。例:「影響を受ける」
5. 得るを使った表現例
5-1. ビジネスでの使用
「市場で優位性を得る」「新規顧客を得る」など、成果や成果物を指す場合に多いです。
5-2. 学術や研究での使用
「実験から新たな知見を得る」「調査結果を得る」など、知識やデータ取得を指します。
5-3. 日常会話での使用
「良いアドバイスを得た」「有益な情報を得た」など、身近な出来事にも使えます。
6. 得ると関連する慣用句
6-1. 得るところが多い
学びや利益が多いことを意味します。
6-2. 得るに易し
簡単に手に入ることを表す古風な表現です。
6-3. 得るところなし
何の利益もないことを意味します。
7. 英語での「得る」表現
7-1. get
日常的で幅広く使える「得る」の一般的訳。
7-2. obtain
努力や手続きを経て得るニュアンスが強い。
7-3. gain
利益や評価など抽象的な対象を得る場合に多用。
7-4. acquire
知識や技術などを習得する意味。
8. 得るを使う際の注意点
8-1. 読み間違いに注意
特に「うる」の用法は日常会話では馴染みが薄く、誤読されやすいです。
8-2. 対象の抽象度に合わせる
物理的な物品には「入手」、抽象的な概念には「得る」や「獲得する」を使い分けます。
8-3. フォーマル度を考慮
ビジネスや公的文章では「得る」を使うと簡潔で品位のある表現になります。
9. まとめ
得るは、物や情報、経験など多様な対象に対して使える汎用性の高い動詞です。「える」と「うる」の読み分けや文脈に応じた類義語の選択が、正確で洗練された文章作成の鍵となります。日常生活から専門的な文章まで幅広く使いこなすことで、表現力が豊かになります。