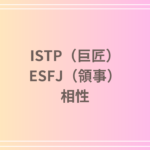「而して」という言葉は古典的な文章や法律文書、書籍などで見かけることがあります。現代では日常会話ではあまり使われませんが、正しい意味と使い方を理解しておくことで、文章力や読解力を高めることができます。この記事では「而して」の意味や用法、例文まで詳しく解説します。
1. 而しての基本的な意味
1-1. 読み方
「而して」は「しかして」と読みます。漢字のまま読むと少し堅い印象ですが、文章では自然に用いられます。
1-2. 基本的な意味
「而して」の意味は主に以下の通りです。 - そして、それに続いて - その上、さらに - それにもかかわらず(文脈による) 文章の前後関係をつなぐ接続詞として使われるのが特徴です。
1-3. 類似語との違い
- そして(単純な接続) - さらに(追加の情報を示す) - しかし(逆接のニュアンス) 「而して」は古典文語的で堅い表現である点が特徴で、現代語の「そして」「それで」に比べて文学的な雰囲気があります。
2. 而しての使い方
2-1. 文語的な文章での使い方
- 古典文学や漢詩、論語のような古典文章では、「而して」は文章をつなぐ役割として用いられます。 例:『君子、学而時習之、而して之を楽しむ』 (意味:君子は学び、時々それを復習し、そして楽しむ)
2-2. 法律文書や公式文書での使い方
- 契約書や規則文書では、論理の流れを明確にするために使用されます。 例:契約当事者は、義務を履行し、而して違反の場合は損害賠償を請求することができる。
2-3. 小説やエッセイでの使い方
- 文語的・文学的な表現として文章を格調高く見せる効果があります。 例:彼は静かに部屋を出た、而して誰もそれに気づかなかった。
3. 而してを使った例文
3-1. 文語的表現の例文
- 学問に励む者は、知識を吸収し、而して実践することが大切である。 - 春風が吹き、花が咲き、而して人々はその美しさを愛でる。
3-2. 法律・公式文書の例文
- 本契約に基づき義務を履行し、而して違反の場合は契約解除の権利を有する。 - 利用者は規則を遵守し、而して違反者には罰則が適用される。
3-3. 文学・小説での例文
- 雨が降り続いた、而して川は増水していた。 - 彼は目を閉じ、深呼吸し、而して静かに決断を下した。
4. 而してのニュアンス・特徴
4-1. 文語的な格式
「而して」は現代語ではあまり使われず、文章に古典的・格調高い印象を与えます。学術論文や文学作品で用いることで、文章全体の品格を上げる効果があります。
4-2. 接続詞としての柔軟性
- 単純な順接 - 追加説明 - 軽い逆接的ニュアンス 文脈によって柔軟に使えるため、読解力を伴う文章表現に適しています。
4-3. 現代語での置き換え
日常会話や現代文では、以下の語に置き換えられます。 - そして - それから - その上 置き換えによって意味は保持されますが、文学的な雰囲気は失われます。
5. 而してを使う際の注意点
5-1. 誤用の例
- 「而して」を無理に会話で使うと不自然になります。 - 例:×今日は忙しかった、而して買い物に行った。 自然な言い回しは「そして」「それから」を使う方が適切です。
5-2. 文脈を意識する
「而して」は文章の接続部分で意味が明確になるように配置する必要があります。前後の文章を読んでつながりが自然になるかを確認することが大切です。
5-3. 過度の使用を避ける
文学的・公式的な印象を出すために何度も使いすぎると、文章が堅苦しく読みにくくなるため注意が必要です。
6. まとめ
「而して」は「そして」「その上」といった意味を持つ文語的な接続詞です。古典文学や公式文書で用いることで、文章に品格や論理の明確さを加えることができます。現代語では使用頻度は低いものの、文章力や読解力を向上させるために理解しておく価値のある言葉です。文脈に応じて適切に使うことで、文章表現の幅を広げることができます。